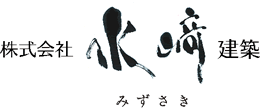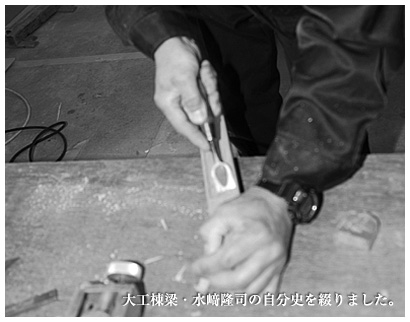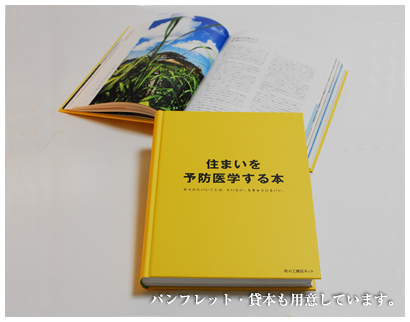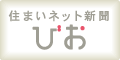木の家は、大工に頼んでほしい。
餅は、餅屋に頼むのがいい。
木の家は、大工に頼んでほしい。
木の家は、大工で決まる。
 「餅は、餅屋」ということわざがあります。今では餅屋は機械で餅を搗いていますが、昔は臼で搗きました。アマもプロも臼で餅を搗いた時代には、餅屋が搗いた餅にはかなわない。やっぱりプロはプロだと思われていたのです。
「餅は、餅屋」ということわざがあります。今では餅屋は機械で餅を搗いていますが、昔は臼で搗きました。アマもプロも臼で餅を搗いた時代には、餅屋が搗いた餅にはかなわない。やっぱりプロはプロだと思われていたのです。
ぼくは、木の家は、大工で決まると思っています。最近では既製品の「階段セット」が建材として売られていて、組み立てれば、たちまち階段が出来てしまうのですが、それでは木は泣いているのではないかと思います。噛み合いの悪い歯は耐え難いでしょ。
あれと同じです。木の性質をよくみて、かちっと噛み合せてやると木はニコニコしてくれます。そのためには、ふだんの大工道具の手入れが大事です。
大工道具と職人仲間
道具を手入れするということは、その道具が持つ最高の力を発揮できる状態におくことです。料理人は、包丁という道具を手にして、魚や野菜と語り合い、料理をつくります。大工は、鉋や鑿といった道具を手にすることで、木を知り、木が持つ生命力を引き出して、家をつくります。木は、伐られて家の材料になったあとも生きていて、呼吸したり、水分を吸ったり吐いたりします。そこが木の家の魅力です。木の家は、大工によって決まるけれど、大工だけで家は造れません。 壁を塗る左官仕事は左官屋さんに限ります
。最近はビニールクロスやサイディングなど、「貼りもの建材」が増えていますが、ぼくは左官仕事がいいと思っています。
壁を塗る左官仕事は左官屋さんに限ります
。最近はビニールクロスやサイディングなど、「貼りもの建材」が増えていますが、ぼくは左官仕事がいいと思っています。
建具は建具屋さんが、畳は畳屋さんがつくります。ここでも「餅は、餅屋」という言葉があてはまります。それぞれ長いつき合いがあり、信頼を寄せる方達です。
自分が納得できる大工仕事をしたと思えたとき、ほかの職方衆も自然とリキが入っているのが分かります。この反応は正直過ぎるほどです。職人どうしは、言葉を交わさなくても、「あ、うんの呼吸」というか、やった仕事で通じます。
木材のこと
 ぼくが建てる家では、柱や梁などの構造材に天竜杉を、土台には天竜桧を用いています。
ぼくが建てる家では、柱や梁などの構造材に天竜杉を、土台には天竜桧を用いています。
天竜材は粘りがあります。粘りがあるということは、強度が高く、目あいが良く、赤味がはり、心地よい肌触り。真っ直ぐで長い材が取れます。雪が多い地域は曲がり材が多くなりますが、天竜は雪害が少ないので、通直な木が育ちやすいのです。天竜杉は、心材の耐久性が高く、長期の水湿にもよく耐えてくれます。また天竜桧は、耐水性・耐久性・加工性に優れ、狂いの少ない材です。
 浴室と洗面所については、能登ひばを用いています。能登ひばは、抗菌作用に優れているヒノキチオールという精油分をたっぷり含んでいて、腐りや水分に強く、水廻りに最適な木です。
浴室と洗面所については、能登ひばを用いています。能登ひばは、抗菌作用に優れているヒノキチオールという精油分をたっぷり含んでいて、腐りや水分に強く、水廻りに最適な木です。
床材と階段の踏み板は、岩手の赤松を用いています。木目がきれいで、樹脂分の多い材なので、経年美しい飴色に変化します。予算に余裕のある家では、強さとねばりのある材なので、梁にも用いています。木材は、適材適所で用いることに尽きます。
ほたて漆喰壁
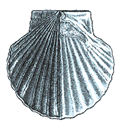 最近、これはいいと思っている壁材に、北海道で生まれた〈ほたて漆喰壁〉があります。日本の家は、木も、壁も、紙も、畳も、湿度が高ければ、それを吸収し、乾燥していれば吐いてくれます。だから木の家は快適なのですが、この調湿性を持った建材が減って、空気を吸ったり吐いたりしないで、汗をかいてしまう材料が増えてきました。
最近、これはいいと思っている壁材に、北海道で生まれた〈ほたて漆喰壁〉があります。日本の家は、木も、壁も、紙も、畳も、湿度が高ければ、それを吸収し、乾燥していれば吐いてくれます。だから木の家は快適なのですが、この調湿性を持った建材が減って、空気を吸ったり吐いたりしないで、汗をかいてしまう材料が増えてきました。
最近、健康にいいとされて珪藻土が流行っていますが、珪藻土がわずか四%程度しか含まれず、繋ぎ材に樹脂を混ぜているものが出回っています。それを健康建材だと宣伝しているのです。〈ほたて漆喰壁〉は、多孔質の性質を持っていて、調湿性の高い材料なので、ぼくはこちらを使っています。砂漆喰が持つような、独得の白さがいいですね。原料となるほたての貝殻は、北海道だけで十万トンもゴミにされていますので、これを用いるのは、ゴミをゴミにしないでリサイクルするのは、環境的にとてもいいことだと思っています。